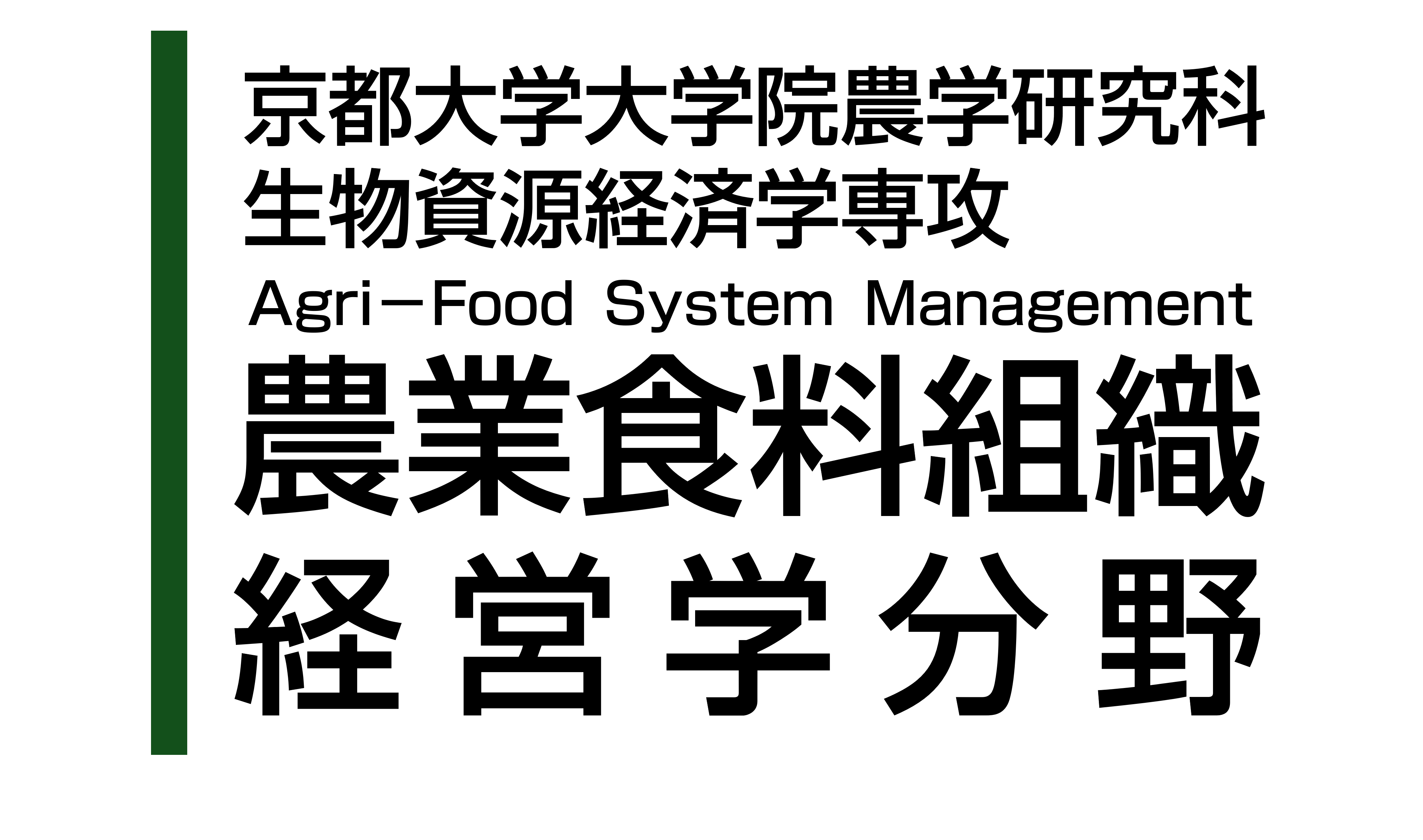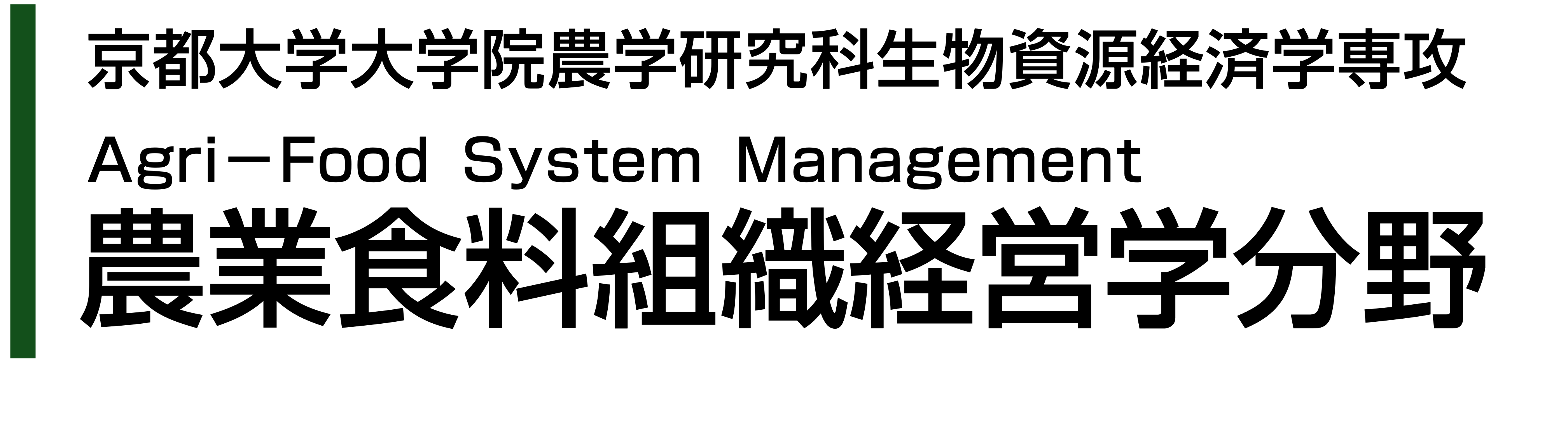research achievements
学位論文一覧
博士論文
2020年
- 上田遥「味覚教育とガストロノミを基礎とした食育に関する研究―「食に関する潜在能力」をもつ食べ手の育成―」
2017年
- 山野薫「社会貢献型農産物に対する消費者の品質情報認識および商品評価に関する研究」
- 大住あづさ「伝統的な地域産品のフードシステムと主体間の垂直的調整に関する研究」
2016年
- 則藤孝志「梅干しのフードシステムの空間構造と産地動態に関する研究」
- 平松(野々村)真希「家庭の食品ロスを生む消費者行動に関する研究」
2015年
- 原田英美「情報処理システムとしての農業経営―経営者の環境認識から見る意思決定」
2014年
- 今泉晶「種子と遺伝情報の管理体制に対する批判的検討―所有の正当化理論とシードシステムに着目して―」
- 山本祥平「食品事業者の危機管理と法令遵守に関する研究」
2012年
- 山口道利 「家畜疾病のコントロール・デザインにおける補償制度の研究:公的補償と民間レベルの損失軽減メカニズムの検討」
- 山口治子「食品安全のためのリスクアナリシスにおける情報ニーズと科学的助言の提供に関する研究」
2011年
- 鬼頭弥生「食品由来リスクに対する態度の構造―日本の消費者を中心として―」
2010年
- 八木俊輔「持続可能なマネジメントの体系に関する研究ー環境経営とCSRの統合理論の構築を目指してー」
2006年
- 鄭銀美「韓国における親環境農産物のフードシステムに関する研究 -持続可能な農と食を求めて-」
2005年
- 山田隆一「ベトナム・メコンデルタの複合農業経営における技術開発計画と経営的評価に関する研究」
- 工藤春代「食品分野における消費者政策の要件と手法に関する研究 -EUおよびその加盟国ドイツを事例として-」
2002年
- 魏台錫「青果物における産地間競争と農協のマーケティング戦略に関する研究」
修士論文
2023年度
- 井出澤茉歩「露地野菜作経営における農共依存要因の解明―都市的地域と中山間地域の比較分析―」
- 末永恭規「日本の地理的表示保護制度の実態と課題―GI制度はどこへ向かうのか―」
- 何艾珈「産直有機農産物の価格形成・信頼構築とオルタナティブ性―北京の有機ファーマーズ・マーケットを事例として―」
- Ndirugendawa Shadia「Chain and Interdependence among Transactors of Coffee Trade between Uganda and Japan: Based on Business Ecosystem and Value Chain Model ウガンダと日本のコーヒー貿易における取引主体間の連鎖と相互依存:ビジネスエコシステムとバリューチェーンモデルに基づいて」
2022年度
- 八尾祐香「道の駅の地域振興機能の発揮プロセス―京都府中山間地域の2駅の実態分析―」
- 神谷萌々子「GFSI 承認規格取得が食品製造企業に与える影響―食品安全システム認証FSSC22000を取得している中小企業を対象にして―」
- 久保文乃「地域づくりの内発性の変遷プロセスとIターン定住者の役割と課題―山口県阿東地域旧亀山小学校の活用を事例に―」
- 佐野颯人「京都市中央卸売市場の近郷野菜部の形成過程とその歴史的背景―立売人が仲卸業者へと至る変遷について―」
- Jung Gyunggeun「地域ブランド農産物に対する消費者のブランド属性評価と価値観―「京のブランド産品」を事例に―」
2021年度
- 文儷潔「生鮮果物の消費拡大におけるカットフルーツの利用可能性―カットフルーツに対する消費者の意識と選好―」
- 張羽馳「中国杭州市における野菜の流通と卸売市場の実態―価格形成システムとIT化を中心に―」
2020年度
- LIU WEITONG「中国北部の農村産業融合の実態—山東省・滕州市大宗村を事例として―」
- 髙田咲「産地再編における組織間構造の変化の解明―宮崎県児湯郡及び西都市を事例にして―」
- 高橋尚子「持続可能な生計アプローチに基づく家族農業経営体の経営発展の分析―発展の方向性・多様性とその要因―」
- LIU XIAONING「中国・張家口懐来県におけるブドウの6次産業化と「道の駅」—農家経営への影響の解明—」
- 宮本明徳「社会的連帯金融としての頼母子講・マイクロファイナンスの評価―庄原市高野町と信用生協の取組みを事例にして―」
2019年度
- 山田将太郎「農村コミュニティと農業者の経営行動における累積的因果連関メカニズムの解明―京都府綾部市坊口町を事例にして―」
- 劉可「高標準農地建設における農民専業合作社の構造と役割―湖北省のレンコン合作社を事例として―」
2018年度
- 石田侑衣「肉用牛繁殖経営の経営継承と新規参入ー困難さの要因とその解決策ー」
- 窪園敦「有機JASマークに関する情報提供の有効性ー経済実験を用いてー」
- 久米祐輔「タンザニアにおける近代的灌漑稲作プロジェクトの農家経済への影響ーキリマンジャロ農業開発計画(KADP)を事例としてー」
- 佐藤秀「アフリカ農業の経営目的の実態とその多様性ータンザニア・キリマンジャロ州の2農村を事例としてー」
2017年度
- 大原調「新規定住者が内発的地域づくりの主体となるプロセスの解明 ―ネオ内発的発展論と質的研究法TEAに基づく事例分析―」
- 董志遠「日本における食品安全に関するリスク管理の実態 ―標準手順書と実際の取組みとの比較―」
- 小野島晴子「民間企業主催の農業体験が農業への興味や関心に与える影響 ―ヤンマーミュージアム体験農園を事例として―」
- 呉喬実「農産物直売所における原価提示型販売の有効性について」
2016年度
- 林和哉「ベトナム産ロブスタ種コーヒーの価格・品質調整の仕組み―生産から輸出までの取引を中心に」
- 松原拓也「生協産直取引における価格形成方法の実態解明―酪農協プラントと地域生協の産直牛乳取引を事例に」
- 酒多佳苗「大規模水田作経営における労働配分の実態とその工夫についての考察―滋賀県彦根市を事例に―」
- 柿原真奈「飼料米事業におけるマッチングシステムに対する一考―近畿地方の事例を用いて―」
- 上田遥「A Comparative Analysis of Taste Education in France, Italy, and Japan in Search for Solutions for the Challenges of Japan’s Food Education (日仏伊における味覚教育の比較分析―日本の食育への示唆―)」
- 泉谷真現子「伝統的地域産品の地域との結び付きの実態と地理的表示法における評価の分析」
2015年度
- 三好晨仁「食中毒リスクコミュニケーションにおける確率的数量情報の認知と伝達に関する研究」
2013年度
- 大隅来「農地貸借における貸し手側の意識と行動―京都府下の2地域を事例に―」
- 多田正徳「畜産物の市場構造と小売業者の買い手パワーに関する実証分析―牛乳と鶏卵を対象に―」
- 村松亜季「地域ブランド認証制度の意義と課題―日本の制度の比較分析を中心として―」
- 林ビジョ「日本向け台湾産愛文マンゴーのフードシステム―F農産物輸出会社を中心とする連鎖構造の事例研究―」
2012年度
- 伊東拓也「企業の農業参入における参入-経営-撤退局面への行政対応の実態と課題 ―全国自治体アンケート調査と撤退事例分析により―」
- 白石奈津子「少数民集落世帯における諸資源の獲得と利用に関する考察 ―フィリピン・ミンドロ島 アランガン・マンヤンの生計構造を中心に―」
2011年度
- 山野薫「社会貢献型農産物の購入に関する消費者意識の研究 ―生協組合員を対象とした選択型コンジョイント分析、コレスポンデンス分析、CVMから―」
- 桂奈菜子「青森りんごの産地生産・出荷構造と輸出体制についての研究」
- 大住あづさ「大かぶ・千枚漬のフードシステムの研究―品質と価格の調整―」
2010年度
- 末岡友行「メキシココーヒー農家の生存戦略ー移民/出稼ぎと農業協同組合に着目してー」
- 津島美琴「地域住民の自治力による農業振興の可能性に関する研究ー長野県・阿智村智里西地区を事例にしてー」
- 野々村真希「家庭における食品ロスー消費者の食品ロスを出す際の心理および食品ロスに至った原因ー」
- 南絢子「生鮮食品の商品選択における消費者の情報処理プロセスー品質判断と内的参照品質ー」
- 薮崎友誉「食品期限表示偽装事件後の企業の対策と消費者の信頼回復のあり方ー赤福表示偽装事件、石屋製菓表示偽装事件を事例にー」
2008年度
- 則藤孝志「ウメのフードシステムの空間構造分析」
- 山本祥平「食品安全上の緊急事態発生時における食品製造業者による対応の評価-低脂肪乳による集団食中毒事件を事例として-」
卒業論文
2023年度
- 秋間友莉子「規格外野菜の販売方法に関する一考察~生産者の販売行動の事例分析から~」
- 井上朋子「企業の社会的責任 (CSR) 事業と有機農業―職場CSAの有機農業普及への貢献度―」
- 北幹貴「海外における日本食レストランの口コミ分析」
- 斎藤友仁「情報提供が消費者選好に与える影響に関する分析―提供する情報内容の違いに着目して―」
- 津川真奈「半農半漁経営における複合化のメリットと持続可能性について―徳島県鳴門市大毛島の事例分析―」
2022年度
- 石河敏啓「日本におけるトウモロコシのフードシステムの実態と変化―用途別の輸入構造と外観図の分析―」
- 奥谷颯太「食品事業者におけるフードロス対策~食品小売店・飲食店を中心に~」
- 堀江亮祐「自治体による農産物認証に対する消費者評価―「兵庫県認証食品」を事例に―」
- 山田優衣「米のマーケティング戦略の実態ー農業者と農協の戦略の比較分析ー」
2021年度
- 田中千尋「担い手と「その他の多様な経営体」との間の連携・協働関係の実態」
- 山口佳那子「Iターン・Uターン新規就農者における就農プロセスと心理的側面の関係の分析~鹿児島県薩摩郡さつま町の事例から~」
- 西村桃香「食品関連企業におけるフードバンクへの食料提供の動機と影響―京都におけるFB活動を事例に―」
- 山口智輝「経営価値四原理システムに基づく有機農業の望ましい展開方向の解明―奈良県宇陀地域の経営体の農業経営分析―」
- 井出澤茉歩「長野県南佐久地域における青果物生産・流通の農協依存の要因―農業経営機能の依存度と農協への期待に着目して」
2020年度
- 祢冝和希「有機農産物の流通チャネルと価格形成の実態ーフードシステムの連鎖構造分析に基づいてー」
- 佐野颯人「卸売市場法の改正から見る卸売市場問題の現状と経営戦略ー京都市中央卸売市場を事例としてー」
- 八尾祐香「ブータンにおける道の駅の役割と課題ー地域振興機能・日本の経験を中心にー」
- 伊賀大祐「商品開発先行型地域ブランドのブランド形成の実態ー草津メロンを事例にー」
- 久保文乃「地域づくりの内発性の変遷プロセスと外部主体の役割ー山口県旧亀山小学校の利活用を事例としてー」
- 坪根遥香「集落営農の経済的・社会的意義の検証ー中山間地域の活性化への手段としてー」
2019年度
- 谷口絹佳「業務用米のフードシステム―需給ミスマッチの存在と影響―」
- 三宅衛「周年雇用型経営の発展プロセスとその課題―東北農業の発展に向けて―」
- 宮田雄介「鶏卵の価格形成方法の実態解明―生産者-卸売業者間の取引を中心に―」
- 山田実穂「農協の事業内容・構造の変化と組合員の企業化―農業企業形態の変化への対応―」
- 廣田雄作「民間企業の農業参入の影響と企業・市町村間協定の存在意義」
2018年度
- 大西節「農事組合法人における事業多角化の影響分析ー酒人ふぁ~むの財務諸表分析を通してー」
- 北村みえこ「国産大豆のフードシステムと価格形成ー輸入大豆との比較を通してー」
- 田飼航平「米の販売戦略で重視される品質」
- 高田咲「食品企業のCSRを促す組織体制・企業文化ー食品企業2社と電子機器企業1社の比較分析ー」
- 眞木理名「現代日本における家族農業の意義」
- 宮本明徳「社会的連帯経済の取組みとその持続性確保の実態ーキョーワズ珈琲のフェアトレード事業を事例にー」
2017年度
- 高橋尚子「施設園芸における家族農業の経営発展の多様性─持続可能な生計アプローチの応用─」
- 中野健人「加工用ばれいしょの契約取引の実態─需給調整の方法を中心に─」
2016年度
- 大前澪「イスラム教徒の日本旅行中の食事の価値観について ―飲食店がハラ-ル対応を行う際の課題―」
- 久米祐輔「ODAによる農業開発プロジェクトの評価方法の検討 ―キリマンジャロ農業開発の経営分析を対象として―」
- 佐藤夏子「食品業界における食品ロス削減の方策」
- 中田吉英「農産物直売所による消費者市民の育成―みずほの村市場におけるアンケート調査を通して―」
- 林田光平「生乳サプライチェーンの不完全競争性と価格伝達―新実証産業組織論による分析―」
- 松下有菜「大学生のサプリメント・健康食品利用と食事内容および意識との関連」
- 吉田旺史「大規模経営体の不確実性に対する投資―生産要素の遊休を通して―」
2015年度
- 大嶋恵里「美山町を中心とした鹿肉のフードシステム」
- 大原調「農村の内発的発展を目的とする、地域外からの協力の在り方について」
- 呉喬実「直売所における価格設定のための原価計算」
- 玉田茜「地域ブランド認証制度の現状と課題―鹿児島県の焼酎・黒酢を事例に―」
2014年度
- 柿原真奈「飼料用米事業における生産者と利用者のマッチングシステムに関する実態研究―京都府を事例に―」
- 角田由貴乃「大学生の食生活とその規定要因―写真投影法を用いて―」
- 佐藤秀「タンザニアにおける農業の持続可能性の評価―キリマンジャロ山中の有機農法転換を事例として」
- 松原拓也「生協産直の価格形成方法の実態と変遷―京都生協と生活クラブを事例に―」
2013年度
- 伊川美保「食品を介した放射性物質のリスク知覚に対してリスクリテラシー・批判的思考が及ぼす影響 ―実験前後のリスク知覚を比較して―」
- 浦井愛「農産物直売所における店頭マーケティングの現状と課題―消費者の意思決定プロセスに着目して」
- 笠原希美「京丹後市における米生産農家の販売先選択の実態」
- 斎藤明日美「日本のフェアトレード発展における倫理的消費者参加の構図 ―ラダリング法によるコーヒー購買動機解明を手がかりにして―」
- 渡邉美沙子「食品市場における大規模小売業者のバイイングパワーに対する法的規制の実態と課題 ―独占禁止法と下請法を中心に―」
- 媚山友仁「九条ねぎのフードシステム―連鎖構造と企業行動を中心に―」
- 谷崎雄大「「広島レモン」の産地発展に関する研究―復活の歴史と現在の課題」
2011年度
- 大隅来「個人農業経営者の意思決定に影響する要因の分析」
- 佐藤まり耶「食品ロス削減の取り組みの現状と課題:食べ残しの持ち帰りを普及させる方策
- 高橋源一郎「農業経営者に求められる経営者能力とその形成過程の研究」
- 多田正徳「鶏卵市場における垂直的パワー・バランスの推計に関する実証分析」
- 村田瑞穂「丹波大納言小豆生産者の生産意欲を決定づける要因 ―京都と兵庫の流通構造・生産体制の比較分析―」
- 白神桜子「米粉の生産・流通構造の実態と課題―米粉パンを事例として―」
- 森井章太「豆腐のフードシステムの分析」
2010年度
- 河口恵梨子「建設業の農業経営の安定化と取引形態-野菜の契約取引の分類を通じて-」
- 白石奈津子「フィリピンミンドロ島山地集落における農家経営と農村開発の構造:農業プロジェクトの評価を中心に」
- 宮森由美子「レベルの違う農業体験が参加者に与える影響について」
2009年度
- 大住あづさ「千枚漬けのフードシステム-契約取引の現状と課題-」
- 桂奈菜子「青森における輸出向けリンゴの生産・流通・輸出体制に関する研究」
- 近藤有希子「参加型農村開発プロジェクトの内発的発展化の可能性-タンザニアにおけるPADEPを事例に-」
2008年度
- 田中大貴「農業生産者の望む経営支援-株式会社農業支援を事例にして-」
- 萬年洋子「地元農業を支える食品製造業と生産者の提携に関する研究-飯尾醸造と契約農家の関係を事例として-」
- 南絢子「消費者の生鮮食品購買における内的参照価格、内的参照品質、店頭小売価格に関する研究-コメと牛乳を対象に-」
- 森川直紀「総合商社の新たな機能と倫理的調達の位置付け-サステナブルコーヒーを事例として-」
- 藪崎友誉「食品表示偽装における原因・背景・課題に関する研究と消費者信頼回復に関する検討-赤福の表示偽装事件を事例として-」